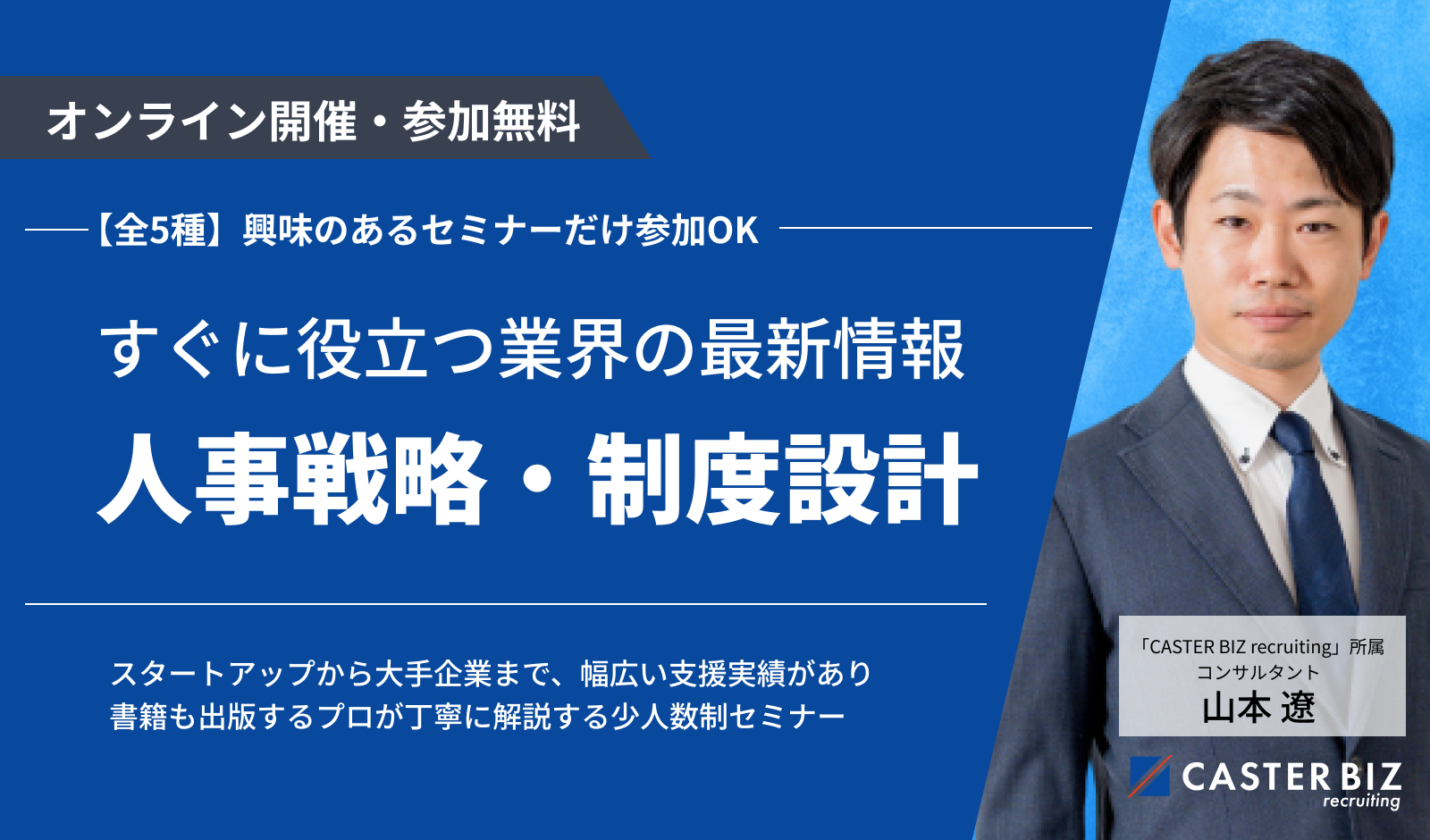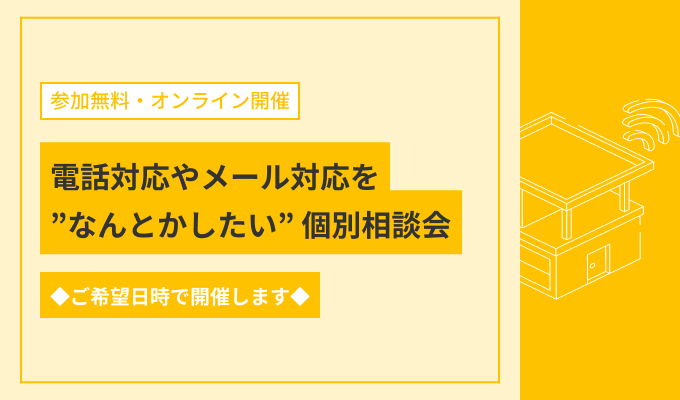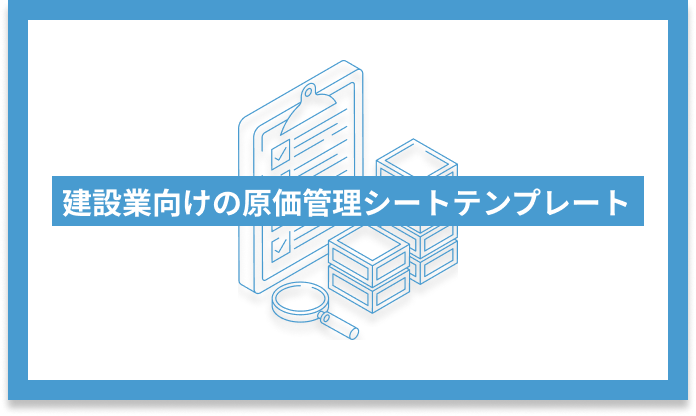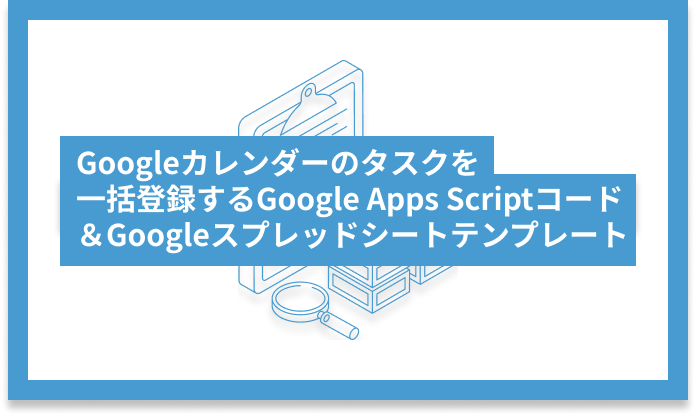さまざまな企業がAI活用を取り入れ始めているなか、現場へのスムーズな導入や活用を促すには経営者やマネジメント層のコミットメントが求められます。まずは何から始めればよいのか、今日からできるAI活用の具体的なシーンと利用例をまとめました。
大企業の経営者が当たり前にAIを活用する時代
2025年2月、株式会社ディー・エヌ・エーが主催イベントにてAIへ積極投資の姿勢を語った際、代表取締役会長である南場智子氏の日常でのAI活用例は大きな話題を呼びました。
南場氏は、AIの力で経営者としても仕事がすごく楽になっていると語り、自身のカレンダーの予定を見せながらどのように生産性を上げているかを紹介。具体的には、まず、初対面の相手が発信している記事や動画を「Perplexity」で検索し、そのリンクを「NotebookLM」にまとめることで最新の考えや活動を効率的に把握。打ち合わせ前には「NotebookLM」に質問して相手のスタンスを素早く確認し、ミーティング中は「Circleback」で議事録とToDoリストを自動生成。投資判断の際には「Deep Research」を使って追加情報を深堀りし、短時間で質の高い意思決定を可能にしているというのです。
ほかにも、大企業の経営者がAIを使いこなしている事例はたくさんあります。
例えば、ソフトバンクグループの代表取締役会長兼社長執行役員・孫正義氏が株主総会でAGI(汎用型人工知能)やASI(人工超知能)について熱く語っているのは有名で、アイデアの壁打ちやディベート相手として日々ChatGPTを活用しています。具体例には、天才的科学者A・B・Cと条件を設定し、「あなたが天才的科学者だとしたら」とテーマを決めてディベートをさせていると話しています。
日本マイクロソフトの社長・津坂美樹氏は、自社製品の生成AI「Microsoft Copilot」(以下、Copilot)を活用。例えば、優先度の高いメールをレコメンドさせたり、会議で議論すべきトピックを整理・分析させたり。また、自分自身が出席しなかった会議の内容をCopilotに要約させることで、迅速かつ効率的に情報を把握しています。
多忙な中、日常的にAIを使うことで、経営者のリソースを効率化し、生産性を上げている事例です。
今日からできる「AI活用」4選
AIをフル活用する経営者が注目される一方で、中小企業の経営者の68.8%が「AIを活用していない」という調査結果(※)も。すでに、AI活用レベルの格差が広がり始めているといえます。
では、具体的にどのようにAIを活用すればいいのでしょうか。まずは、今日からでも活用を始めやすい具体的なシーンを4つ挙げました。
※フォーバル GDXリサーチ研究所「中小企業の次世代戦略への対応調査」
1. 議事録の作成
経営者は、毎日いくつもの会議に出席して意思決定する必要があります。そのため、AIを使った会議の議事録作成はもはやマストです。
自分自身がすべての会議に出席できなくても、AIがすぐさま議事録を作成してくれて、会議の内容をキャッチアップできます。
南場氏が使用しているという「Circleback」のほか、「Notta」「SecureMemoCloud」「AmiVoice ScribeAssist」「Rimo Voice」「tl;dv」などさまざまなサービスが出ています。文字起こしだけでなく、要約やタスク抽出までしてくれるサービスもあるので、用途やそれぞれの特徴をふまえて、自身に合ったものを選ぶとよいでしょう。
2. 面会相手の情報収集
経営者は、社内外のさまざまな人と会うのが仕事の1つです。とくに社外の相手と会う前には、相手についての下調べが必要になります。どんな分野でどのように活躍しており、どういう主張や興味関心、思想を持った人なのか、どんなビジネス状況にある人なのか、これらの情報収集にAIはぴったりです。
まず、「Perplexity」などの探索系AIを使い「○○さんについての必読記事は?」と尋ねると、関連するインタビューやメディア記事のURLを一覧で示してくれます。リンクや情報は、「NotebookLM」にアップロードしておくと便利です。NotebookLMに「この方は最近どんな発信をしていますか?」などと聞けば、まとめて要点を整理・表示してくれます。
「Bing Chat」を活用すれば、SNS上の評判などインターネット上の最新情報もチャット感覚で集められます。専門性の高い領域や最新の研究成果を調べたいときには、「Elicit」のようなリサーチ特化型AIも役立ちます。学術論文や調査レポートを要点だけ要約してくれるため、短時間で深い知見を得られるでしょう。
必要に応じてオリジナルソースを確認することを忘れないようにしつつ、下調べに費やす時間を大幅に短縮することができます。
3. 高度なリサーチ
投資判断や戦略構築など、大きな決断を迫られる際には、より深い情報収集が欠かせません。
「Deep Research」を活用すれば、市場動向や競合情報、学術論文など専門性の高いデータソースにまでアクセスし、最新の統計やエビデンスをまとめて提示してもらえます。業界トレンドから企業の財務データまでを俯瞰的に整理し、議論の前提をしっかり固めることも可能です。
レポートや企業のIR情報など、普段は読み込むのに時間がかかる資料もAIがポイントを要約してくれ、短い時間でエッセンスを掴めるのがメリット。もちろん、出力結果だけを鵜呑みにせず引用元や統計の裏付けの確認は必要ですが、個人のリサーチ作業だけでは発見しにくい新たな視点を得られ、意思決定の質が向上するでしょう。
4.アイデアの壁打ち
新規事業の発想や革新的な戦略を練る際にも活用できます。
たとえば、「ChatGPT」に「あなたは○○分野の第一人者です。現状の業界課題にどうアプローチしますか?」と指示を与えることで、自分では想定できないような視点や突飛なアイデアを生成することも可能です。さらに、「A=経済学者」「B=哲学者」「C=生物学者」などと役割を設定し、同じテーマを複数の専門視点で議論させれば、広範囲な可能性を短時間で検討できるメリットがあります。
さらに、AIに自社の強みや市場データをあらかじめ読み込ませておけば、より自社の現状に沿った提案が得やすくなります。
「自ら使い倒す」経営者・マネジメント層のスタンスが求められる
企業で新しい技術や施策を導入する際、重要になるのは経営者やマネジメント層などトップのコミットメントです。コロナ禍にリモートワークの導入が進んだ際も、現場に任せきりではなく、トップがいかにコミットするかが導入スピードや運用に大きな影響を与えたことは明らかでした。
AI時代の今、求められるのはトップが「自らAIを使い倒す」スタンスです。新たなツールが登場すると「まずは現場から」と考えがちですが、経営者が率先して使いこなし、具体的な事例を示すことで、社内全体がAI活用へ移行しやすくなります。
AI領域は凄まじい勢いで進化を続けています。この変化・進化をどう先取りし、どのように事業や組織変革へつなげていくかを考え抜く姿勢こそが、企業の未来を左右すると言えるかもしれません。
使いこなせれば大変便利なAIですが、どうやって導入すれば良いかわからないという方も多いでしょう。本メディア『Alternative Work』を運用するキャスターでは、ビジネスや組織課題に合わせたAIエージェントをフルカスタマイズで制作し、要件定義・実装・保守まで一貫してサポートするサービス「CASTER NEO(キャスターネオ)」を提供しています。ご相談は、以下よりお問い合わせください。
https://ai-agent.cast-er.com/contact.html

さくら もえMOE SAKURA
出版社の広告ディレクターとして働きながら、パラレルキャリアとしてWeb媒体の編集・記事のライティングを手掛ける。主なテーマは「働き方、キャリア、ライフスタイル、ジェンダー」。趣味はJリーグ観戦と美術館めぐり。仙台の街と人、「男はつらいよ」シリーズが大好き。ずんだもちときりたんぽをこよなく愛する。
メールマガジン

仕事のヒントが見つかる情報をお届けしています。