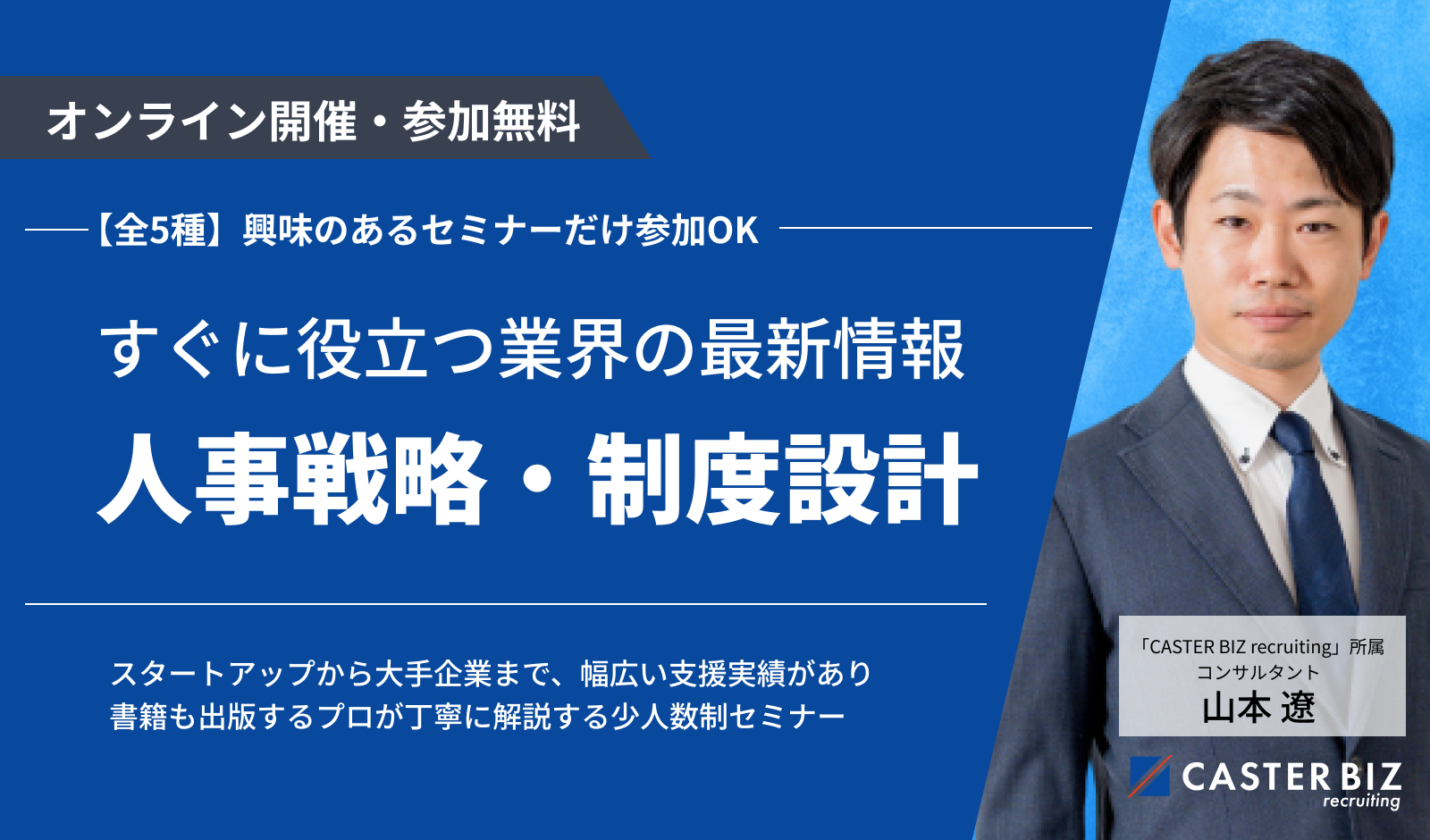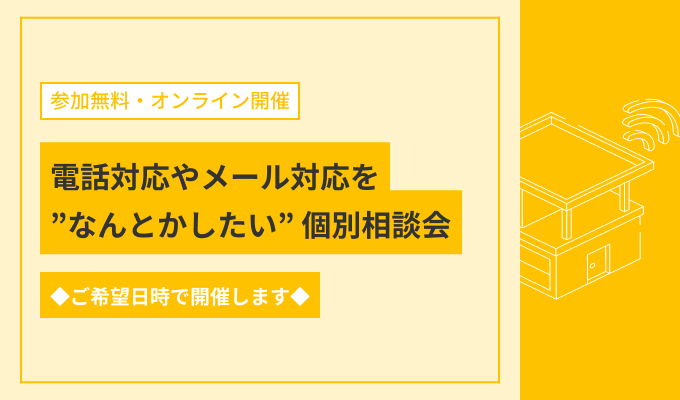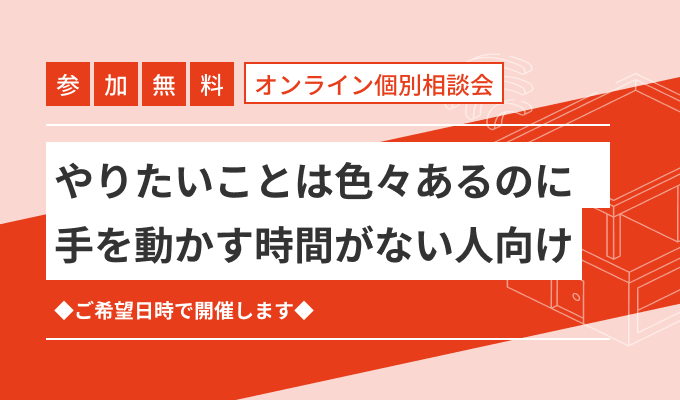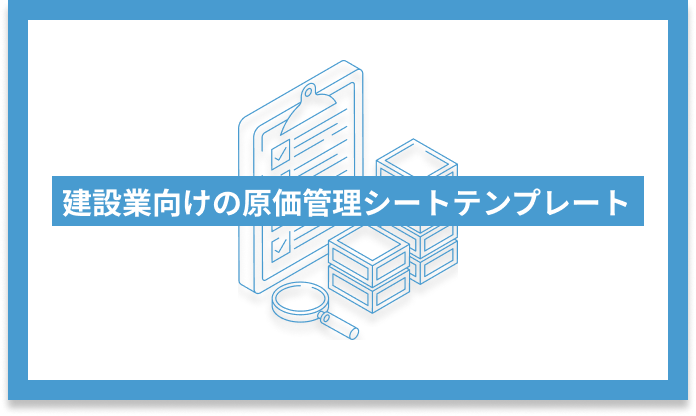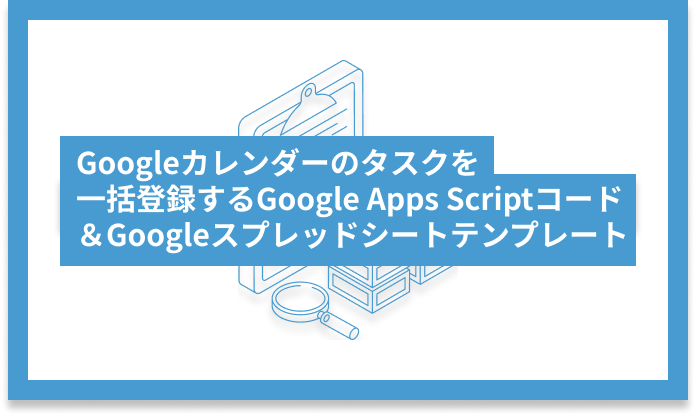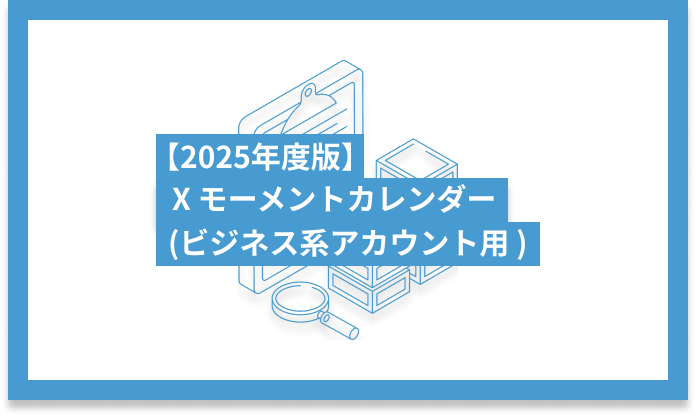2025年春の大卒の内定率が過去最高の92.6%というニュースが話題ですが、実は今、高卒者の求人倍率も空前の高まりを見せています。実際、高卒人材の採用計画を大幅に増加する大手企業も少なくありません。高卒求人が注目される背景と実態について調べました。
高卒者の求人倍率は過去最高に
文部科学省によると、2024年3月卒の高卒者の求人倍率は全国平均で3.98倍(※1)。これはつまり1人の高校生を約4社が取り合っているという状況で、まさに「超売り手市場」。バブル期を超え、過去最高を記録しています。
大卒の求人倍率が1.75倍である(※2)ことと比べても高い状況で、2025年卒においてはさらに高い求人倍率になるとも予想されています。なお、東京都に限れば、高卒者の求人倍率はなんと9.84倍(23年3月卒、※3)にまで跳ね上がります。大手企業が集まり求人も多い都市部では、さらに顕著な傾向のようです。
とくに工業高卒者や高専生の人気が高く、2023年3月卒の工業高卒者の求人倍率は過去最高の20.6倍(※4)を記録。就職内定率は99.3%と非常に高い水準です。働く現場で必要なスキルや技能を高校の授業で経験していたり、業務に直結する資格を取得していたりするため、即戦力としての魅力が高いことが理由と考えられます。
また高専生は、研究開発や生産管理、生産現場などで多く活躍しています。求人倍率は20倍を超え、就職率は例年ほぼ100%を達成(※5)。現場を支える若く優秀な人材として、安定したニーズがあります。
※1:令和5年度「高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職・就職内定状況」
※2:リクルートワークス研究所「大卒求人倍率調査(2025年卒)」
※3:厚生労働省「令和5年3月新規学校卒業者求人・求職・就職状況」(令和4年9月末現在)
※4:全国工業高等学校長協会「卒業者等に関わる状況調査」(令和5年10月)
※5:国立高等専門学校機構「国立高専機構 概要」
人手不足を背景に、製造業や小売、建設業を中心に採用
なぜ、これほどまでに高卒人材の人気が高まっているのでしょうか。最大の理由は、人手不足です。現在日本のビジネスシーンでは、業種・業態によらず人材不足が慢性化しています。少子高齢化で若手人材の確保が難しくなるなか、大卒に加えて高卒を積極採用していくことで、人手不足を改善しながら若手人材の層を厚くできます。企業が、戦略的に人手不足を解決する手段として、高卒求人が注目されているといえます。
実際、高卒採用を行っている企業に理由を聞くと、「若手人材の層を厚くするため」が70.4%、「人材不足のため」が50.8%、「高卒採用が自社に合っているため」が29.3%という回答結果に(※6)。
また、業界ごとの高卒者の就職先は、製造業が39.9%と圧倒的1位で、卸売業・小売業(10.6%)、建設業(8.6%)と続きます(※7)。数ある業界の中でも人手不足が著しいとされる業界で、特にものづくりやサービス、建設の現場を担う人材として、高卒者がさかんに採用されていることがわかります。
国内の大手企業でも、高卒者の採用計画を大きく伸ばしている例があります。例えばヤマト運輸は5割増、セコムグループは3割増を計画しています。
※6:株式会社ジンジブ「高校新卒採用 企業動向調査」
※7:『学校基本調査』文部科学省
経営者や人事担当者が考えるべきポイント4つ
こうした状況を受けて、経営者や人事担当者にはどんなポイントが求められるでしょうか。4つにまとめました。
高校生に伝わるような育成ビジョンをつくる
研修カリキュラムや人材育成計画、キャリアプランなどを明確にし、どんなカリキュラムに沿って研修が行われるのか、その結果どんな人材として育成されるのか、キャリアの選択肢にはどんなものがあるのかといった要素を明示する必要があります。
とくに若手は、就職先に「自分が成長できる環境」を求める傾向にあります。どのようなキャリアを描けるのか明らかにすることで、職場としての魅力を上げ、より幅広い人材に自社を選んでもらうことができるでしょう。
採用のミスマッチ防止
高卒者の3年以内離職率は、2024年10月時点で38.4%(※8)と高い傾向にあります。大卒者でもよく課題にあがる「ミスマッチの防止」が、高卒人材においてはより重要といえるでしょう。
高卒求人独自のルールもあります。例えば、学生は学校を通じて就職活動をするため、学校と企業の関係性に左右されてしまう要素があり、学生の囲い込みが発生しがちです。また、学生は原則として一度に1社しかエントリーできない、いわゆる「一人一社制」があります。
そのため高校生は、就職活動の過程で志望動機をブラッシュアップしたり、他社と比較しながらエントリーする企業のよさを知ったりする機会が少ないといわれます。結果的に、学生本人の意に沿わない就職先に進まざるをえないケースも多いとされます。
そのため、企業側はミスマッチの防止と入社後の定着の工夫が必要です。例えば、職場見学の時点で業務内容を具体的に紹介したり、入社後は現場の状況を定期的にヒアリングしたり、現場のコミュニケーションをフォローしたりといった施策が考えられます。また学生向けの情報発信も重要です。HPやSNSで、現場の様子を写真や動画をまじえて紹介したり、イベントで実際に働いているメンバーを紹介したりすることで、高校生にもイメージしやすくなるでしょう。
就職支援サービスの活用
大卒の就活市場と比べると少数ではありますが、近年、高校生に特化した就職支援サービスも出てきました。2024年に新規でグロース上場した企業もあります。
大卒者の就職支援サービスは多数あり、webで誰でも簡単に大量の情報にアクセスできます。しかし高卒の場合、就職活動における主な情報源は、ハローワークの求人票や所属している学校の教師です。求人票には掲載情報の制限があるうえテキストベースの掲載に限られ、教師からの情報も限定的になりがちです。
企業側も、就職支援サービスを利用して高校生によりわかりやすく情報発信したり、就職先の選択肢として自社を知ってもらうきっかけを作ったりする工夫が必要です。
給与・評価制度の見直し
ここ数年、大手企業を中心に次々と賃上げが行われています。もともと、大卒と高卒では平均年収が異なることが、多くの高校生が大学進学を目指す理由にもなっていました。大卒の賃上げ潮流に合わせて、高卒者についても待遇改善が必要といえます。
例えば、積水ハウスの子会社である積水ハウス建設ホールディングスは、積極的に高卒者を採用する方針で、2023年4月に高卒新入社員の初任給を11%引き上げました。24年4月には、前年の3倍超となる134人の高卒者が技能者として入社しています。
高校生は、毎年9月頃から始まる採用試験に向けて早めに準備を進めます。企業側も優秀な人材を確保できるよう、今から対策を進める必要があるでしょう。
※8:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します」
『Alternative Work』では、定期的にメルマガを配信中!ニュース、時事ネタから仕事のヒントが見つかる情報まで幅広くお届けします。ぜひ、ご登録ください。
登録はこちら

さくら もえMOE SAKURA
出版社の広告ディレクターとして働きながら、パラレルキャリアとしてWeb媒体の編集・記事のライティングを手掛ける。主なテーマは「働き方、キャリア、ライフスタイル、ジェンダー」。趣味はJリーグ観戦と美術館めぐり。仙台の街と人、「男はつらいよ」シリーズが大好き。ずんだもちときりたんぽをこよなく愛する。
メールマガジン

仕事のヒントが見つかる情報をお届けしています。