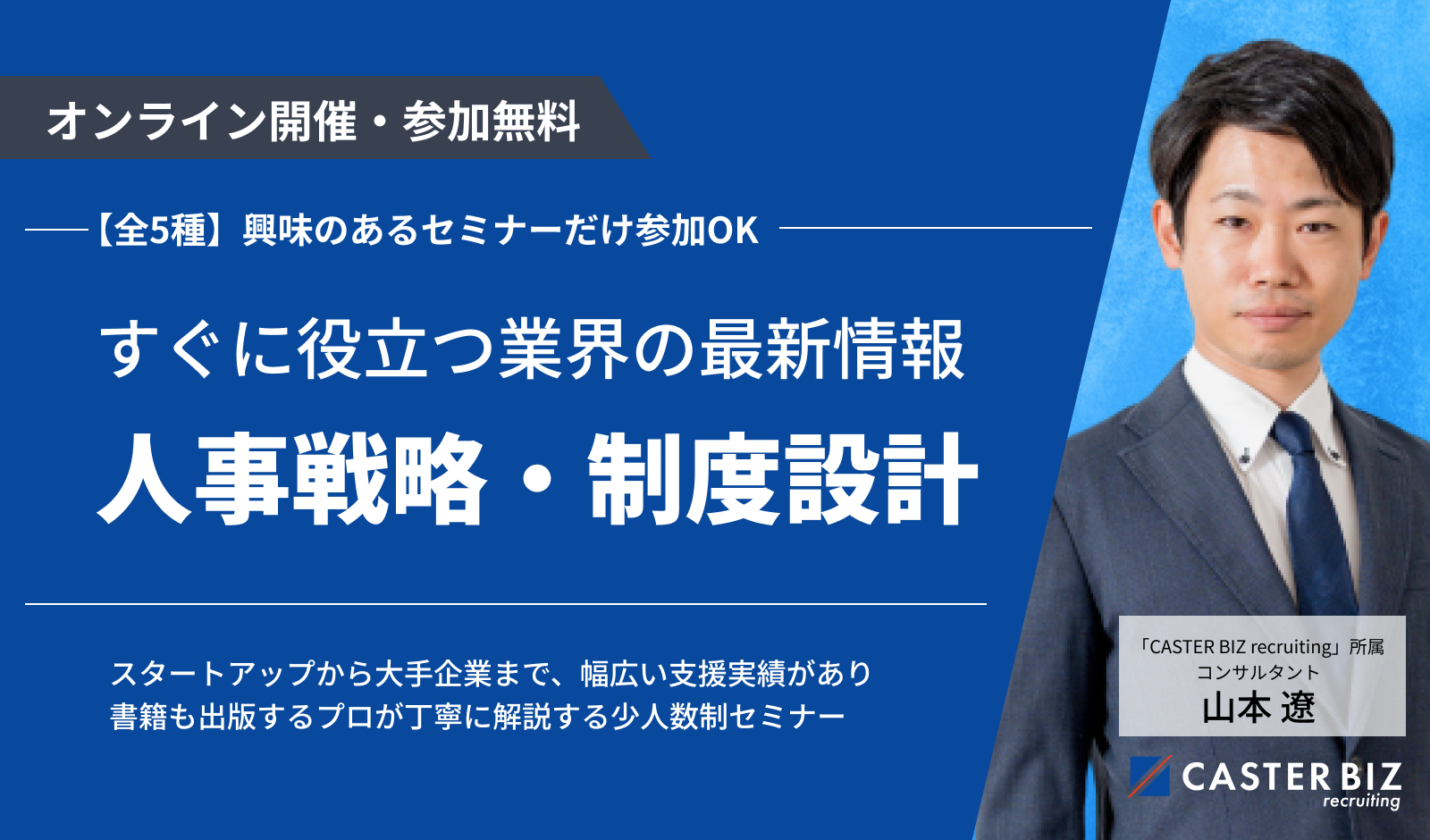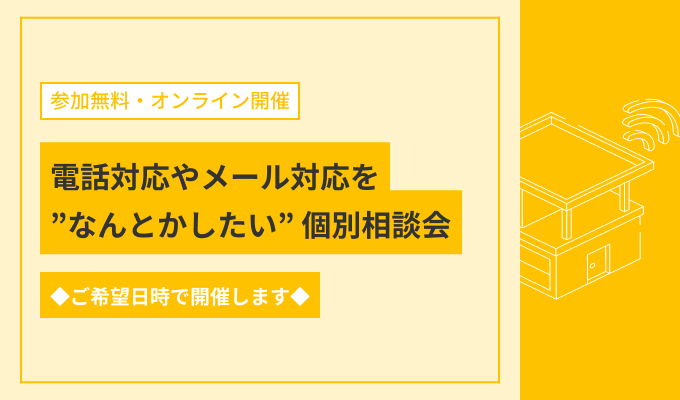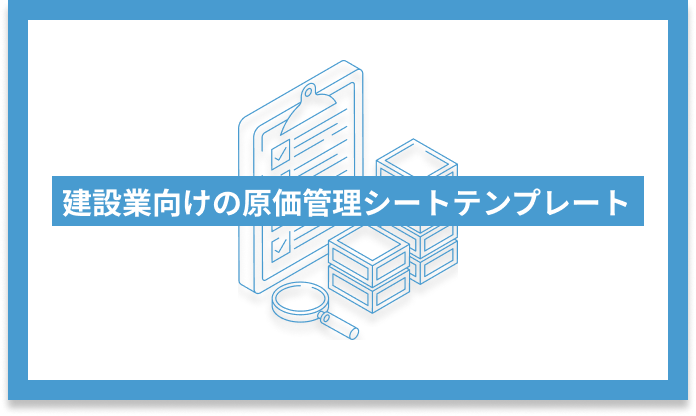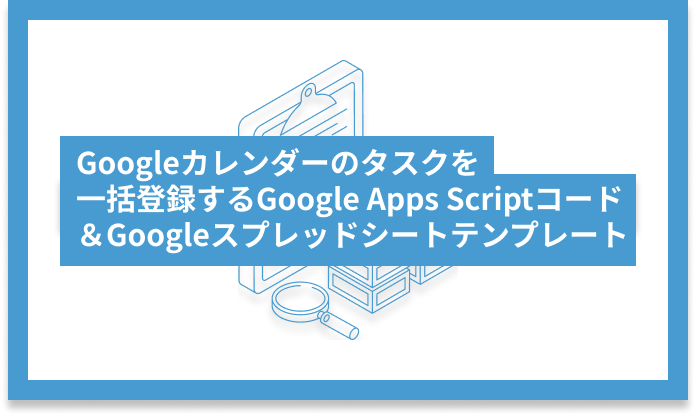人手不足が深刻化し、いわゆる日本型雇用システムが崩れつつある今。注目されているのが「イグジットマネジメント(退職マネジメント)」の概念です。本記事では、その中身や具体的な取り組み方について探ります。
若手も対象!イグジットマネジメントとは何か?
イグジットマネジメントとは、自社のメンバーが納得のいく形で退職を迎えられるためのマネジメントを指します。イグジット(exit)は日本語で「出口」。別名、「人材マネジメントの出口戦略」「退職マネジメント」とも呼ばれます。
イグジットマネジメントには、離職の防止策や退職時の手続きはもちろん、メンバーが自分のキャリアを考え、退職を含むさまざまな選択肢を自分で選ぶためのサポートも含まれます。また、別の視点で考えると、メンバーが退職を迎えるまでの準備を通して、企業側が「メンバーをどのように送り出したいか」を具体的に考えることともいえます。
イグジットマネジメントは、ベテランやシニア人材だけに関係する概念ではないのがポイントです。転職は、誰にでも与えられた選択肢。どのメンバーも、退職する可能性を秘めているといえます。
企業がイグジットマネジメントを適切におこなうことで、メンバーは自分が退職するまでの過程をポジティブかつ具体的にイメージし、モチベーションを保ちながら働けるようになり、結果的に自身のキャリアを長期的に描くことにつながります。
人材不足が顕著な昨今は、出口よりも入口、つまり「いかに優秀な人材を採用し、労働力を確保するか」に注目が集まりがちです。しかし、出口を戦略的に考えることで、採用とは違った観点からメンバーのモチベーションやエンゲージメントを上げ、企業の人材戦略に貢献できるといえます。
なお、イグジットマネジメントと混同されやすい言葉に「リテンションマネジメント」があります。これは、リテンション(維持)とマネジメントを掛け合わせた造語で、メンバーの離職を防ぎ、その能力を発揮できる状態をつくる人事施策です。
リテンションマネジメントは人材の定着を第一の目的とするため、メンバーの長期的な満足度向上を目指し、働きやすい環境づくりを目指します。たとえば、エンゲージメントの向上や働きがいの充実、ワークライフバランスの安定化などに向けた取り組みがあげられます。
日本型雇用システムの終焉や、深刻な人材不足が背景に
今、イグジットマネジメントが注目されているのはなぜでしょうか。
背景の1つに、日本型雇用システムが終わりつつあることが挙げられます。以前は「新卒一括採用」「終身雇用」「年功序列の賃金体系」など日本独自の雇用システムが多くの会社で採用されていました。
しかし、最近はとくに「新卒一括採用」「終身雇用」が崩れつつあります。転職が一般化しており、マイナビの調査によれば、2023年の正社員転職率は7.5%(※1)で過去最高水準となっています。
※1:マイナビ「転職動向調査2024年版」
背景の2つ目は、シニア人材のモチベーション維持です。近年は、シニア人材がビジネスの現場で活躍しています。パーソル総合研究所がまとめたデータによると、65~69歳の就業率は50.8%、70歳以上の就業率は18.4%で、10年以上増加し続けています。
※2:パーソル総合研究所「働く10000人の成長実態調査2023~シニア就業者の意識・行動の変化と活躍推進のヒント」
2025年4月からは、企業に「65歳までの雇用確保(定年の延長や廃止、再雇用制度の設置)」が完全義務化されることにもなっており、シニアにいかにモチベーション高く働いてもらうかが、経営者の命題になっています。
ごく一部の企業を除き、再雇用後の待遇は、定年前と比べて大幅に下がるのが一般的です。金銭面だけでなく、長年磨いてきたスキルが陳腐化したり、つかみ取ったポストから外れることへの喪失感があったりして、同じ熱量で働けないシニアが多いのも事実です。
イグジットマネジメントに取り組むことは、企業の新陳代謝を促進しつつ、ベテランやシニア人材のモチベーション維持にもつながります。
現役メンバーには「離職防止とキャリアサポート」の両輪で
若手や中堅メンバーに対するイグジットマネジメントとしては、2つの施策が考えられます。1つは、「離職防止」の策を取ること。人手不足の中、優秀な人材は各社から引っ張りだこになる時代です。離職を防ぐためには、やりがいを感じられる業務内容や待遇向上はもちろん、働く環境の改善や、成長を実感できる制度づくりなどが必要です。
もう1つは「キャリアに関するサポート」です。離職に関わらず、個々の志向やスキルセットに合わせて長期的なキャリア設計をサポートするのもイグジットマネジメントの1つです。
一度離職を決意したメンバーがその決断を覆す可能性は非常に低いとされます。メンバーが自律的にキャリアを考えられるようサポートし、出した結論を受け入れ応援することこそ、企業側ができるサポートといえるでしょう。
シニア人材に向けた「3種類のイグジットマネジメント」
定年が迫りつつあるベテランやシニア人材に対しては、選択肢として3種類のイグジットマネジメントが存在します。それぞれの特徴と注意点を紹介します。
1.積極雇用型
本人が希望する限り、定年前と同じ程度の業務や働き方、待遇を維持し、活躍できる環境をつくるもの。なるべく変わらない環境で働き続けられる状態を目指します。本人もモチベーションを保てるうえ、会社も即戦力をそのまま雇用し続けられるのが大きなメリット。一方で、部下の昇進を妨げない工夫や、人件費がかさむ点には注意です。
2.メリハリ型
会社側が、シニア人材の雇用条件や働き方にいくつかの選択肢を用意し、本人の意欲や希望に応じて決定するもの。あくまでも本人の考えやライフスタイルを尊重しつつ、双方が納得できる形に落とし込めるのがメリット。選択肢が増える分、会社側には丁寧に向き合う時間や制度設計が求められます。
3.転身支援型
メンバーの転職や独立など、転身をサポートするもの。会社側には、メンバーがほかの職場でも通用するスキルを身につけるサポートや、メンバーのキャリア相談にのるなどの施策が求められます。転身を促進する分、人件費をおさえられるのがメリット。一方、進め方次第ではメンバーのモチベーションにネガティブな影響をもたらす可能性がある点に注意です。
イグジットマネジメントの進め方3ステップ
イグジットマネジメントを始める際、どのような順序で取り組むといいのでしょうか。進め方の3ステップをご紹介します。
1つ目は、イグジットマネジメントの趣旨と必要性を社内に周知することです。イグジットマネジメントの概念は、まだ深く知られていません。なぜやる必要があるのか、組織と個人にどんなメリットが見込めるのか、自社の事情に合わせて設計し、説明する必要があります。
2つ目は、自社が採用するべき施策を具体的に検討することです。施策によって、メリットはもちろん、企業側で必要になる調整、リソースも異なります。現場で働くメンバーの声や人事部門の考えも踏まえて、現実的なラインを探ることが必要です。
3つ目は、メンバーからフィードバックを受け、施策をブラッシュアップすることです。イグジットマネジメントは従業員体験(EX)の向上にもつながるため、メンバーからの意見や要望を集めるのも大切なことです。
本メディア『Alternative Work』を運営するキャスターでは、人事労務のプロが事業成長、働き方改革に伴う人事労務の課題を丸ごと解決するサービス「CASTER BIZ HR」を提供しています。イグジットマネジメントをはじめ、人事労務のご相談は以下よりお問い合わせください。
CASTER BIZ HR
さくら もえMOE SAKURA
出版社の広告ディレクターとして働きながら、パラレルキャリアとしてWeb媒体の編集・記事のライティングを手掛ける。主なテーマは「働き方、キャリア、ライフスタイル、ジェンダー」。趣味はJリーグ観戦と美術館めぐり。仙台の街と人、「男はつらいよ」シリーズが大好き。ずんだもちときりたんぽをこよなく愛する。
メールマガジン

仕事のヒントが見つかる情報をお届けしています。